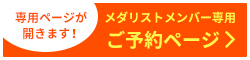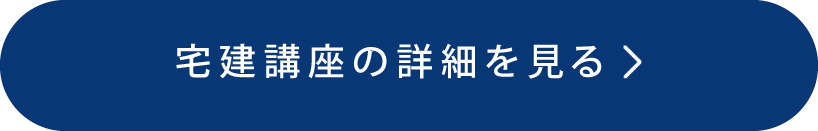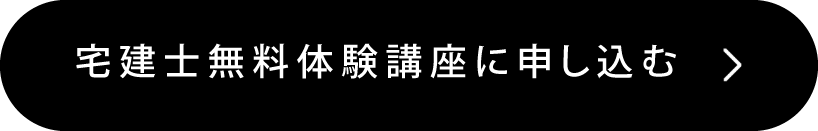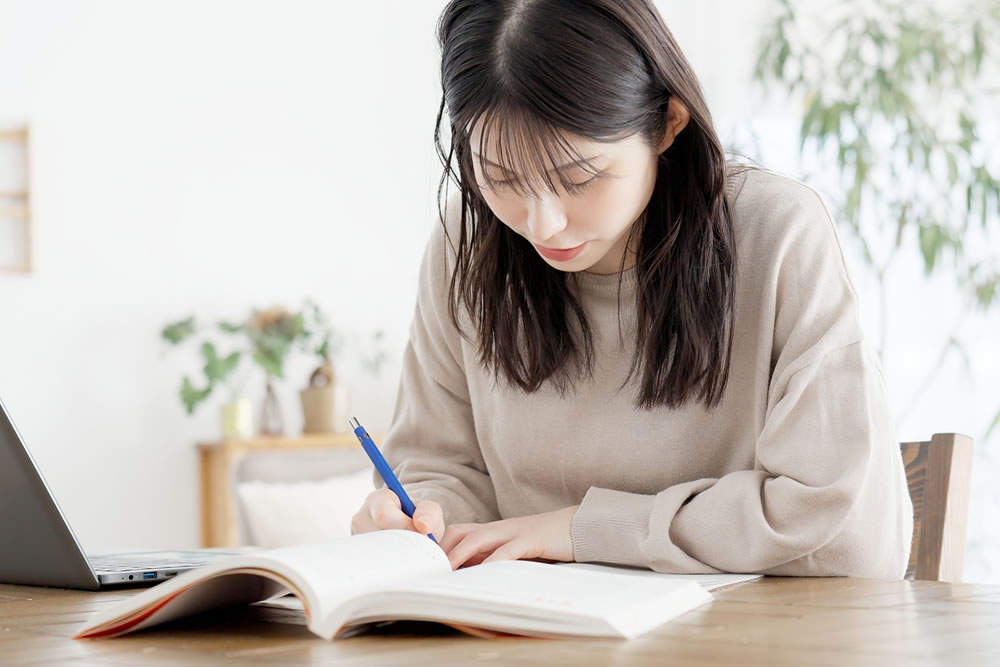【初心者向け】宅建試験に合格するための勉強法!最短で合格を目指す3ステップ
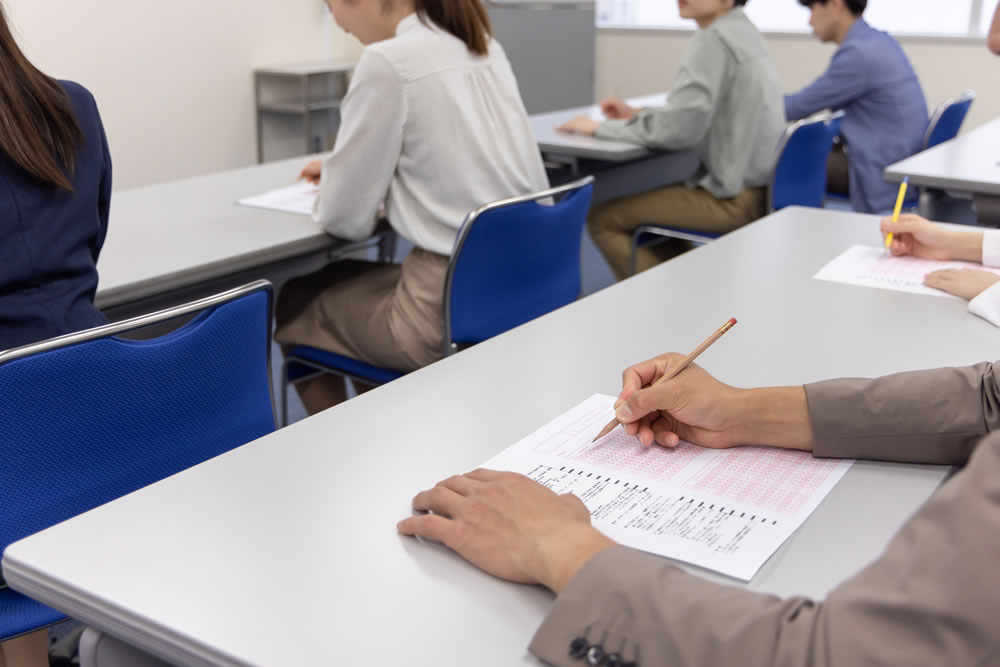
- カテゴリー
- タグ
-
- #宅建業法
このページは約7分で読めます。有意義なページになっていますので、最後までご覧ください。
「宅建の勉強を始めたいが、何から手をつければいいのかわからない」
「独学で本当に合格できるのか不安」
「効率の良い勉強法を知りたい」
宅建試験は毎年20万人以上が受験し、合格率は15〜18%前後と決して簡単ではありません。特に宅建試験初心者の方は勉強法がわからず、途中で挫折するケースもあるでしょう。
しかし、正しい勉強法を実践すれば、宅建初心者の方でも短期間で合格を目指せます。重要なのは、基礎を固め、計画的に学習し、過去問を活用することです。
そこでこの記事では、初心者向けの宅建試験の勉強法を詳しく解説します。独学と講座の違い、試験に落ちやすい人の特徴、効率的な学習方法まで幅広く紹介しますので、宅建試験に挑戦する方はぜひ参考にしてください。
初心者でも宅建試験に合格できる!その理由とは?
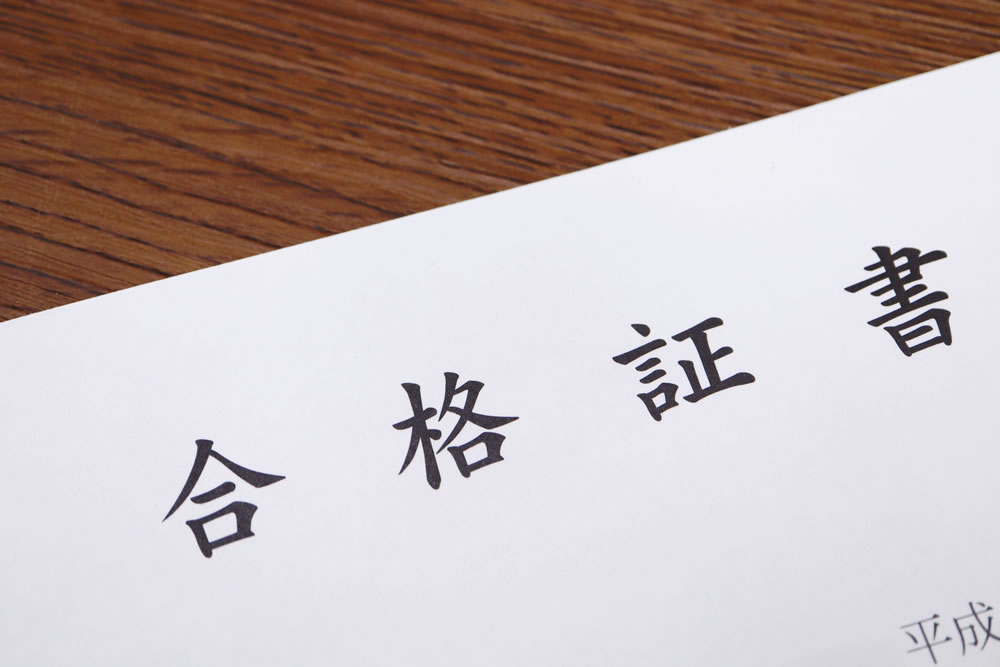
宅建試験は難関資格とされていますが、適切な勉強法を実践すれば初心者の方でも合格は十分可能です。実際、毎年多くの受験者が合格しており、独学でも対策しやすい試験といえます。
過去の合格率
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 当該年の合格率 |
| 令和5年 | 233,276 | 40,025 | 17.2% | ー |
| 令和4年 | 226,048 | 38,525 | 17.4% | ー |
| 令和3年(12月試験) | 24,965 | 3,892 | 15.6% | 16.8% |
| 令和3年(10月試験) | 209,749 | 37,579 | 17.9% | |
| 令和2年(12月試験) | 35,261 | 4,610 | 13.1% | 15.4% |
| 令和2年(10月試験) | 168,989 | 29,728 | 17.6% |
引用:一般財団法人 不動産適正取引推進機構|試験実施概況(過去10年間)一部引用
近年の宅建試験の合格率は毎年15〜18%前後で推移しており、他の国家資格と比較しても高めです。また、宅建試験には3つの特徴があります。
・合格率が安定
大きな変動がなく、一定の対策を続ければ合格可能
・出題傾向が固定
試験範囲が明確で、過去問学習が効果的
・学習環境が整っている
通学講座(スクール)やオンライン講座、市販のテキストやスマホアプリが充実
特に「宅建業法」は配点が高く、繰り返し出題されるため、短期間でも得点しやすい分野です。
しかし、独学では重要ポイントを見極めるのが難しく、効率よく学習を進めるには専門講師のサポートを活用するのがおすすめです。
初心者が宅建試験に合格するための3ステップ
宅建試験に合格するには、効率的な学習が欠かせません。基礎固め、計画的な学習、過去問対策の3つを押さえることで、初心者の方でも合格が可能です。
1. 基礎を固めるための学習方法を知る
まずは試験の出題範囲を理解し、学習の優先順位を決めることが重要です。宅建試験は「宅建業法」「権利関係」「法令上の制限」「税・その他」の4分野に分かれており、その中でも宅建業法は配点が高く、得点源になりやすいため最初に学ぶのが効果的です。
効果的な学習方法は、以下の3つです。
・テキストで基礎知識を学ぶ
・問題集で理解を深める
・アプリなどを活用しスキマ時間に復習する
まずはテキストを1周して全体像をつかみ、その後問題演習を中心に進めると効率的です。
2. 効率的に学習を進めるためのスケジュールを作る
宅建試験合格には200〜300時間の学習が必要とされます。無計画な学習は非効率になりがちなので、余裕をもったスケジュールを立て、段階的に学習を進めることが大切です。
以下は、学習スケジュールの例です。
・1~2ヶ月目:テキストを1周し、試験範囲を把握
・2~4ヶ月目:問題集を解きながら知識を定着させる
・4~6ヶ月目:過去問を解き、本番形式に慣れる
・6ヶ月~:模擬試験で本番を想定する
さらに、通勤時間や昼休みなどのスキマ時間を活用すれば、忙しい人でも学習を継続しやすくなります。
3. 過去問と模試で実践力を高める
宅建試験では、過去問と類似した問題が多く出題されるため、過去問演習が合格の鍵となります。
過去問・模試の活用法は、以下の方法を参考にしてみましょう。
・過去10年分の問題を解き、出題傾向を把握する
・間違えた問題は解説を読んで理解し、重点的に復習する
・宅建業法の問題を優先的に解き、確実に得点できるようにする
・模試を受け、本番と同じ時間で解く練習を行う
過去問と模試を繰り返すことで、本番で時間配分を意識しながら解答できる実践力を養えます。
独学or講座?初心者が迷わず選べる宅建試験の勉強法
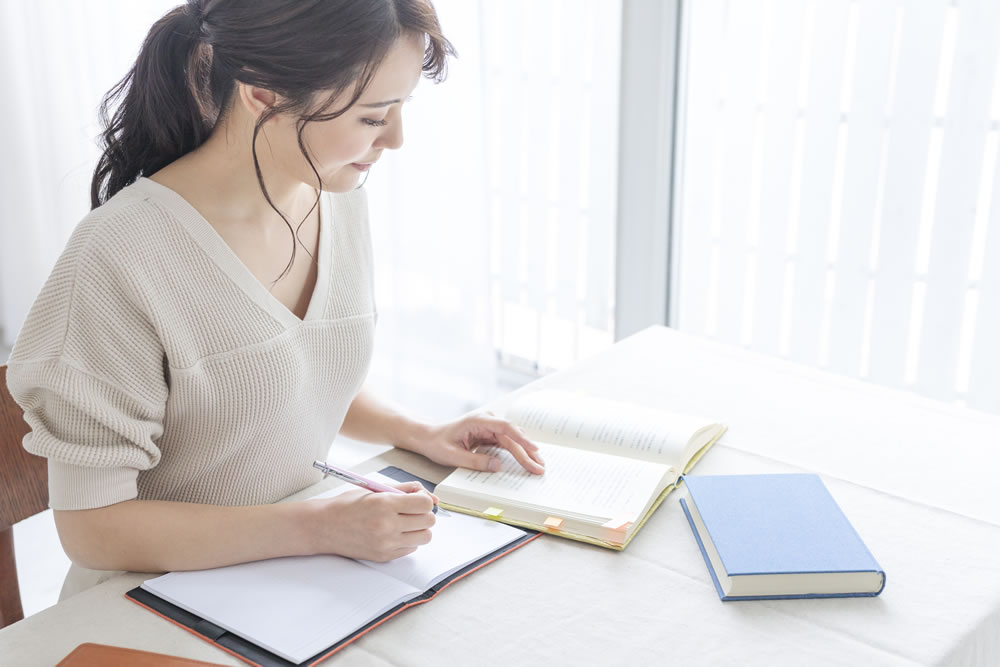
宅建試験の学習方法には「独学」「スクール」「通信講座」の3種類があります。それぞれにメリットと注意点があり、自分に合った方法を選ぶことが合格への近道です。
ここでは、「スクール」と「通信講座」を同じカテゴリーとして扱い、それぞれの特徴を比較し、どの学習法が適しているのか判断しやすいように解説します。
1. 独学で挑戦するメリットと注意点
宅建試験は独学でも合格可能ですが、効率的な学習法を選ぶことが重要です。独学にはコストを抑えられるメリットがある一方、自己管理が求められます。
| メリット | デメリット | 向いている人 |
| ・費用が安い・自分のペースで学習できる・教材を自由に選べる(テキスト・アプリ・動画) | ・計画的に進めないと挫折しやすい・わからない部分の解決が難しい・過去問対策を怠ると点が取れない | ・費用を抑えたい人・自分で計画を立てて学習できる人・調べながら学ぶのが得意な人 |
独学で合格するためには、適切な教材選びと計画的な学習が必要です。自己管理ができる人にとっては、低コストで効率的に合格を目指せる方法といえます。
2. スクールや通信講座を利用するメリットと注意点
スクールや通信講座を利用することで、効率よく学習を進められます。特に、初めて宅建を学ぶ人や独学に不安がある人にはおすすめです。
| メリット | デメリット | 向いている人 |
| ・講師の解説で理解しやすい・効率的な学習カリキュラムがある・質問できる環境が整っている | ・独学よりも費用がかかる・学習時間の自由度が低い(特にスクール)・講座選びを間違えると非効率 | ・独学に自信がない人・短期間で合格を目指したい人・費用をかけても確実に合格したい人 |
スクールや通信講座は、費用はかかりますが、短期間で確実に合格したい人には最適な方法です。学習の効率を重視するなら、プロの指導を受けるのも一つの手段です。
宅建試験に落ちる人の3つの共通点

宅建試験に不合格となる人には共通する原因があります。ここでは、宅建試験に落ちる人の3つの共通点について詳しく解説します。
1. 勉強時間が足りていない
宅建試験合格には200〜300時間の学習が必要とされています。試験範囲が広いため、十分な学習時間を確保しないと知識が定着せず、不合格の要因になります。
例えば、1日1時間の学習では6ヶ月以上かかりますが、週に数日しか勉強しないと学習ペースが遅れ、試験前に焦ることになります。特に社会人は、通勤時間や昼休みなどのスキマ時間を活用し、1日2〜3時間を確保することが理想です。
計画的に学習を進め、試験日までに十分な勉強時間を確保することが合格への第一歩となります。
2. インプットばかりでアウトプットが不足している
テキストを読むだけでは知識は定着せず、試験本番で活かせません。不合格になる人の多くは、「テキストを読むこと=勉強」と考え、問題演習を後回しにしがちです。
知識を定着させるには、学習時間の50%以上を問題演習に充てることが理想です。具体的な方法は、以下のとおりです。
・テキストを1回読んだら、すぐに対応する過去問を解く
・間違えた問題の解説を読み、再度解く
・10年分の過去問を最低3周繰り返す
アウトプットを増やすことで、実践力が身につき、試験本番で確実に得点できるようになります。
3. 過去問の解き方を間違えている
宅建試験は過去問をしっかり解けば合格しやすい試験ですが、誤った取り組み方をすると効果が半減します。よくある失敗例は、以下のとおりです。
・解答を丸暗記する(本番で少し違う形で出題されると対応できない)
・解説を読まず、正誤だけを確認する(知識が深まらない)
・最新の試験傾向を意識せず、古い問題ばかり解く(法改正に対応できない)
正しい過去問演習の方法として、間違えた問題をノートにまとめ、解説をしっかり読むことが重要です。また、本番と同じ時間で模試を解くことで試験の時間配分に慣れることも必要です。
過去問を効果的に活用することで、得点力を高め、合格に近づけます。
初心者が効率よく学ぶ!宅建講座を活用する3つのメリット
宅建試験に合格するには、効率的な学習方法を選ぶことが重要です。独学でも合格は可能ですが、知識の定着には時間がかかることがあります。一方、宅建講座を活用すれば、短期間で合格レベルに到達しやすいというメリットがあります。
ここでは、宅建講座を活用する3つのメリットを解説します。
1. 独学では得られない分かりやすい解説とサポートが受けられる
宅建試験は専門用語が多く、特に「権利関係」などの法律分野は初心者の方にとって難解です。独学では理解に時間がかかることもありますが、宅建講座なら専門講師の解説を受けられ、短時間で効率よく学習できます。
また、多くの講座には質問サポートがあり、疑問点をすぐに解決できるのも大きなメリットです。例えば、オンライン講座では動画解説やチャット機能を活用でき、移動時間を有効活用しながら学習できます。
わからない箇所をそのままにせず、スムーズに学習を進められる環境が整っていることが宅建講座の大きな強みです。
2. 最新の試験傾向に対応したカリキュラムで学べる
宅建試験では毎年法改正があり、最新情報の把握が合格のために重要です。独学では情報収集に手間がかかりますが、宅建講座を利用すれば、試験に直結する最新の学習内容を効率的に学べます。
また、講座では過去の出題傾向を分析し、頻出テーマを重点的に学習するカリキュラムが組まれています。直前対策講座や模試付きコースを活用すれば、試験直前の実践力も養えるでしょう。
出題形式の変更や細かいルールの改正にも対応しやすいため、独学よりも効率的に対策を進められます。
3. 短期間で効率よく合格を目指せる
宅建講座を活用する大きなメリットは、短期間で合格レベルに到達できることです。独学では、学習計画を立てる時間や、効率的な学習法を見つけるまでに試行錯誤が必要ですが、宅建講座では、効率的なカリキュラムに沿って学ぶことで、最短ルートで合格を目指せます。
例えば、短期集中コースではインプットとアウトプットをバランスよく組み合わせ、重要ポイントを絞って学習できます。また、進捗管理や学習サポートがある講座なら、モチベーションを維持しながら学習を進められます。
宅建試験の合格率は毎年15〜18%ですが、適切な学習方法を選べば短期間での合格も十分可能です。限られた時間を有効活用し、最短で合格を目指したい人には宅建講座の活用が最適な選択肢となるでしょう。
まとめ|初心者は宅建講座を活用して合格を目指そう!

宅建試験に合格するには、基礎を固め、計画的に学習し、過去問で実践力を高めることが重要です。独学でも合格は可能ですが、効率よく学ぶには正しい学習法と継続できる環境が不可欠です。
特に、試験範囲が広く法律の理解が必要な宅建試験では、専門的な解説と最新の試験傾向を押さえた学習が合格の鍵となります。確実に合格を目指すなら、メダリストクラブの宅建講座を活用しましょう。
メダリストクラブの宅建講座は、専門講師のサポートと最短ルートのカリキュラムで効率よく学習できます。今から始めれば、試験本番までにしっかり準備が可能です。宅建合格への第一歩を、メダリストクラブの講座で踏み出しましょう。