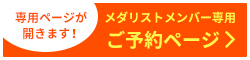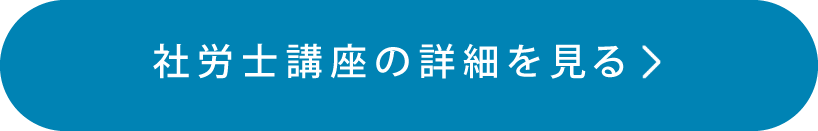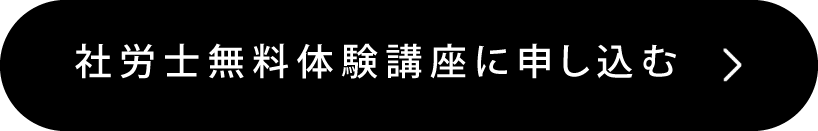社労士試験合格に必要な勉強時間は?働きながらでも合格できる効率的な学習法
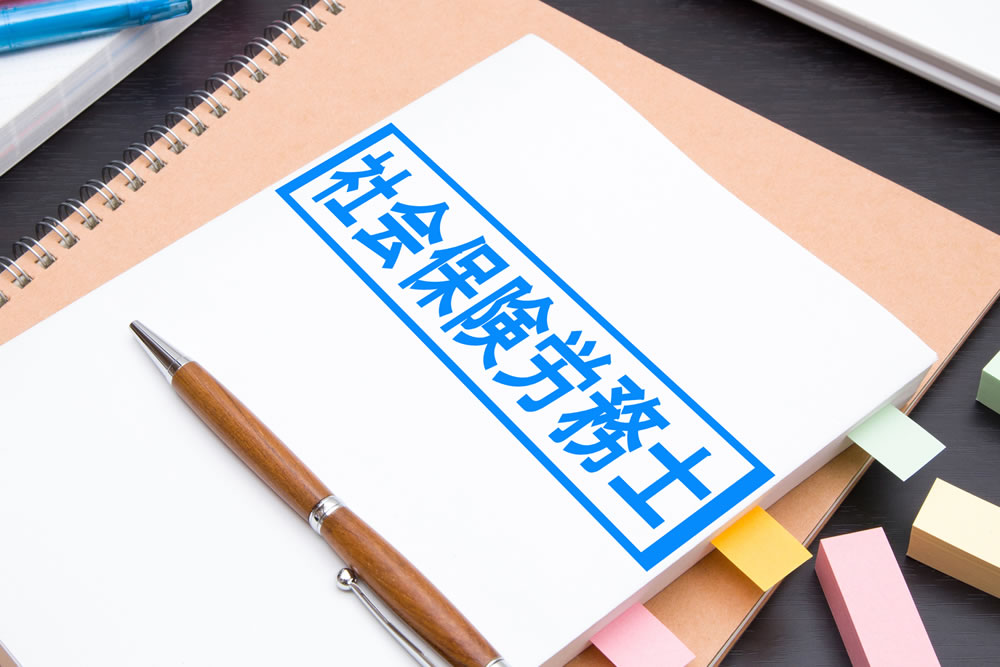
- カテゴリー
このページは約6分で読めます。有意義なページになっていますので、最後までご覧ください。
社労士試験合格に必要な勉強時間はどれくらい?初学者・経験者別の目安やスケジュールの立て方、効率的な学習法をわかりやすく解説。働きながらでも合格するための秘訣もご紹介します。

社会保険労務士(以下「社労士」)試験は国家資格の中でも難易度が高いとされていますが、合格者はどれぐらい勉強時間を確保しているのでしょうか。この記事では、合格に必要な総勉強時間の目安を、勉強方法別で解説。さらに、働きながら挑戦する人のためのスケジュール例もご紹介します。自分の状況に合った学習計画の参考にご覧ください。
社労士試験合格に必要な勉強時間は?
社労士試験合格のための勉強時間は、一般的には800〜1,000時間といわれています。
800〜1,000時間というと少しわかりづらいので、以下のようにイメージしてみてください。
| ・平日土日問わず毎日2時間ずつ勉強する場合 およそ13〜17ヶ月 ・平日2時間ずつ、土日5時間ずつ勉強する場合 およそ10〜12ヶ月 ・平日土日問わず毎日6時間ずつ勉強する場合 およそ4〜6ヶ月 |
この勉強時間はあくまで目安であり、勉強開始前の知識レベルや、勉強方法(独学か資格予備校等を利用するか否か)などの前提条件によって変動します。初学者でも、努力や工夫次第ではこの目安の勉強時間を大幅に下回って合格できる場合もあります。
社労士試験の勉強時間が800〜1,000時間といわれる理由
社労士試験は、なぜ800〜1,000時間という長期間・長時間の勉強時間が必要といわれるのでしょうか。それは主に、以下の3つの理由があると考えられます。
| ①試験科目が多い ②相対評価の試験であり試験の合格率が低い ③法改正が頻繁に行われる |
社労士試験の試験科目
社労士試験の主要試験科目は以下の通り10科目です。
1.労働基準法
2.労働者安全衛生法
3.労働者災害補償保険法
4.雇用保険法
5.労働保険の保険料の徴収等に関する法律
6.労働一般
7.社会保険一般
8.健康保険法
9.厚生年金保険法
10.国民年金法
さらに社労士試験は、選択式試験と択一式試験の二段階で構成されており、それぞれに科目ごと・総合点の基準点が設定されています。
試験科目が多く、苦手科目を作れない仕組みになっている点が、長時間の勉強時間を必要とされている一因といえるでしょう。
社労士試験の合格率
社労士試験の合格率は、過去10年間の平均値で5.9%、中央値で6.4%です。社労士試験は相対評価の試験であるため、合格率は毎年一定水準以下に保たれています。
| 試験実施年度 | 合格率 |
| 2015年(平成27年) | 2.6% |
| 2016年(平成28年) | 4.4% |
| 2017年(平成29年) | 6.8% |
| 2018年(平成30年) | 6.3% |
| 2019年(令和元年) | 6.6% |
| 2020年(令和2年) | 6.4% |
| 2021年(令和3年) | 7.9% |
| 2022年(令和4年) | 5.3% |
| 2023年(令和5年) | 6.4% |
| 2024年(令和6年) | 6.9% |
| 平均 | 5.9% |
社労士試験の出題科目は法改正が多い
社労士試験は手続きに関する法律からの出題が多いため、あらゆる国家資格試験のなかでも、特に法改正の影響を受けやすい試験といえるでしょう。
試験要項では、出題される法改正の範囲は、毎年その年の4月時点までのものです。社労士試験の試験科目のいずれかにおいては毎年法改正が行われており、法改正部分は試験の上でも重要ポイントとなりやすいため複数年受験している人にとっては知識のアップデート作業が必要になります。
この点も、多くの受験生を苦戦させている一因といえるでしょう。
その他の国家試験の勉強時間は?
社労士試験以外の難関国家資格試験合格に要する勉強時間をご紹介します。
| 資格試験 | 勉強時間 |
| 弁護士 | 5,000時間以上 |
| 司法書士 | 2,000~3,000時間 |
| 土地家屋調査士 | 1,000~1,500時間 |
| 中小企業診断士 | 800~1,000時間 |
| 社会保険労務士 | 800〜1,000時間 |
| 行政書士 | 600~1,000時間 |
その他の資格試験に関してもあくまで目安の勉強時間ですが、このように見ると社労士だけが特別に長い勉強時間が必要というわけではないことがわかるでしょう。
また、ここでご紹介している勉強時間は勉強方法や工夫によって短縮できたり、逆にこれより長くかかってしまうこともあります。
【勉強方法別】社労士試験合格までの勉強時間
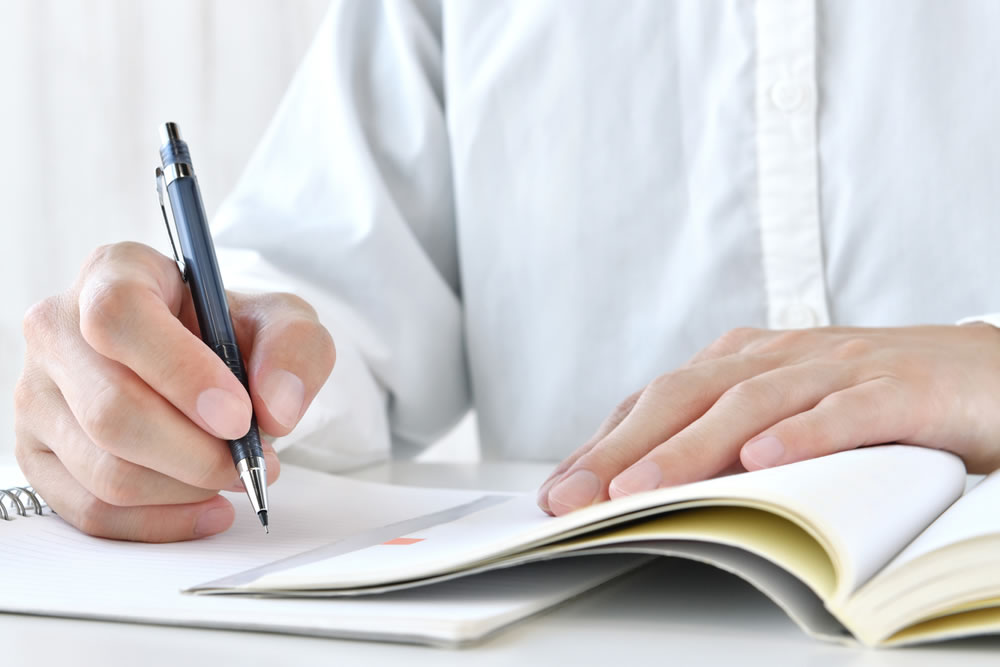
前章までは、受験者全体の目安勉強時間についてご紹介しました。この章では勉強方法別で必要となる勉強時間について解説します。
独学の場合
独学の場合、必要となる勉強時間の目安は1,000時間以上と考えるのがよいでしょう。
社労士試験の勉強の中では、専門的な法律用語や難解な判例が頻出します。法律の勉強自体が初めての方であれば、最初はそのような専門用語や、判例の独特な言い回しに慣れるまでに時間がかかるでしょう。
また社労士試験は、違う科目でも似たような論点が多数存在し、共通点と細かい違いが紛らわしく整理しながら理解・暗記していく必要があります。
独学でも努力を重ねることで合格基準に達することは可能な試験ですが、相当の時間がかかることを覚悟した方がよいでしょう。
資格予備校を利用する場合
資格予備校に通う場合は、600〜800時間程度の勉強時間が目安になります。
資格予備校では難解な条文や論点でも初学者の方にもわかりやすく説明してくれたり、わからないことがあれば講師に個別で質問ができたりするので理解のスピードは独学よりも早まることが期待できます。
また、勉強方法や学習スケジュールなどについても専門のスタッフに相談できる場合もあるので、受験というもの自体に慣れていない方でも効率的な学習を進めることができるでしょう。
社労士試験は試験範囲が広範で、暗記量も膨大です。試験本番が近づいてくると精神的な負担も大きくなってくることもあるため、なるべく時間を無駄にせず効率的に勉強を進められるよう、資格予備校を利用することをおすすめします。
社会人が働きながら勉強時間を確保する方法
社労士試験は難関試験ですが、合格者の約8割はなんらかの仕事をしながら受験した方々であるというデータが公表されています。どのような工夫をして勉強時間を捻出したか、実際の合格者の声をもとに方法をご紹介します。
参考:厚生労働省|第56回社会保険労務士試験の合格者発表|[参考4]合格者数等の推移(過去10年)・第56回社会保険労務士試験合格者の年齢別・職業別・男女別構成
生活のリズムを規則正しく整える
多くの社会人は日中8〜10時間ほど、勤務時間として拘束されていると考えられます。朝型・夜型いずれにしても、寝る時間や起きる時間を調整して勉強時間を捻出するのがほとんどになるでしょう。
例えば朝型の人は早く起きられるようにするために、前日の夜の過ごし方を見直す必要があります。お酒を飲みすぎないように勉強期間中は酒量を決める、朝の身支度の時間を短縮するために前日夜のうちに用意できるものはなるべく用意しておく、などです。
ある程度決まった生活リズムを習慣化することで、身体的なストレスを軽減しつつ自分自身の意識も保つことができるでしょう。
スキマ時間を有効活用する工夫
通勤中や仕事の合間の休憩中など、スキマ時間は意識すればさまざまなタイミングで存在するものです。しかしなかなか教材を広げるに至らずスキマ時間を有効活用できない、ということはよくあるのではないでしょうか。
腰が重くなりがちな勉強を「始める」という点にハードルがあるのであれば、「始める」ことが容易になるような工夫をしてみましょう。重たい教材を開くよりも、「今日は5分あったらこれだけ覚えよう」というメモを作っておいて、それを取り出しやすいところに配置しておくなどです。些細なことですが、ぐっとハードルが下がるので試してみてください。
その他にも、やらないといけないにも関わらず腰が重くなったりストレスに感じてしまうことは、なるべくハードルを下げるということを意識して克服していきましょう。
より短時間で合格するための、効率的な時間の使い方

社労士試験は根気強く勉強を続けていけば合格水準まで到達できる試験ではありますが、1回の受験で合格できたという方の割合は多くはありません。ここでは、できるだけ短期間で合格水準に到達するための効率的な勉強方法についてご紹介します。
PDCAサイクルを意識した学習を心がける
PDCAとはPlan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)の頭文字をとった言葉で、主にビジネスシーンで使用されていますが、勉強を進めていくうえでも重要な観点です。
具体的には以下のように、状況に応じて計画〜改善を繰り返すことを「PDCAサイクル」といいます。
| Plan(計画)…合格から逆算した学習計画を立てる。 Do(実行)…インプットやアウトプットなど、計画したことを実行する。 Check(評価)…過去問演習や模試の受験などで、完成度をはかる。 Action(改善)…計画どおりにいっていない点を洗い出し、それを改善するための策を検討する。 Plan(計画)…検討した改善策を、その後の計画に盛り込みさらに実効性のある計画を立てる。 |
勉強の進捗によって、自分に何が不足しているか、その時何をすべきかということを明確化することができるので、無駄を排除し効率的に実力を伸ばしていくことができるのです。
逆に、無計画に勉強を進めてしまうと自分の実力レベルに合わない勉強をしてしまう→勉強時間は確保できているのに必要な実力レベルに達しない→試験までの日数が足りない、ということになりかねません。
限られた時間のなかで最大限の成果を求めるためには、効率を重視した行動をとっていくことが重要です。
類似点や共通点はまとめてインプットする”横断学習”を心がける
こちらも効率化を目的とした勉強方法です。
社労士試験は主要10科目で構成されています。これらの法律の勉強を進めていくと、似ているようで少し違う、違うようで内容は同じ、など混乱しやすいポイントが多く、このような項目は試験問題として出題された際に引っかかってしまいやすいところになります。
このようなポイントは科目を横断して共通点や相違点を理解・暗記することで効率的に勉強を進めることができるので、必ず整理しましょう。
まとめ
最後に、この記事の要点をまとめます。
◉社労士試験合格に必要な勉強時間の目安は800〜1,000時間
◉効率的に短期間で社労士試験合格を目指すなら、資格予備校を利用するのがおすすめ
◉働きながらでも、工夫次第で短期合格可能
社労士試験は、必ずしも長時間・長期間の勉強が必要というわけではなく、勉強方法や日々の心がけによって短期合格が狙える試験です。コツコツと正しい努力を積み重ねることが、合格への一番の近道であるといえます。

メダリストクラブの社労士講座なら独自にカスタマイズしたオリジナル教材で合格に向けた効率のよい試験対策が可能です。
これから社労士資格の勉強を始めたい人は、ぜひメダリストクラブの社労士講座を検討してみてください。