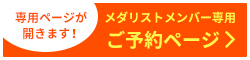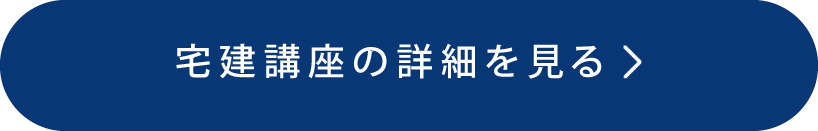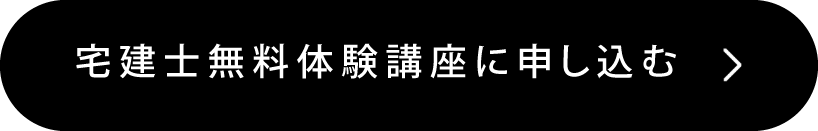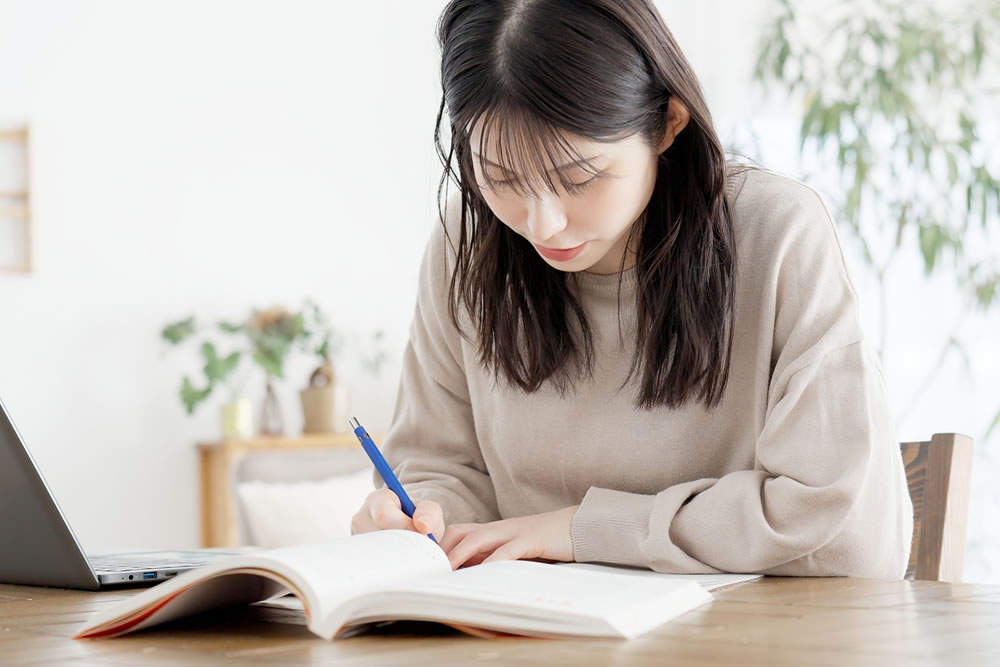宅建試験直前に覚えること完全ガイド!合格へ導く重要ポイントと暗記法
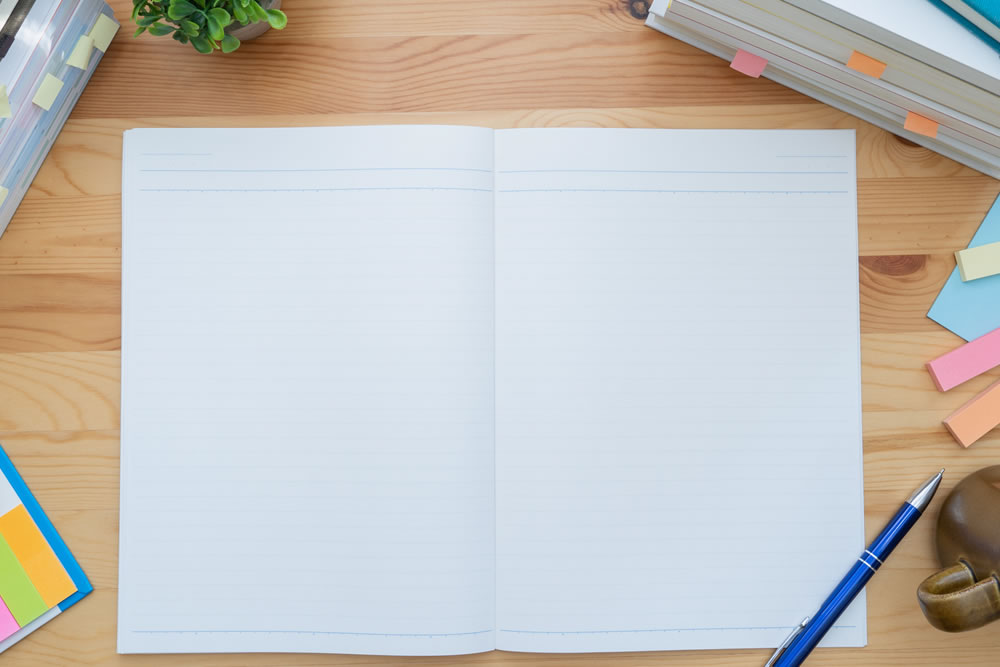
- カテゴリー
- タグ
このページは約7分で読めます。有意義なページになっていますので、最後までご覧ください。
宅建試験直前に覚えること完全ガイド!合格へ導く重要ポイントと暗記法
「試験まで残りわずかだけど、何から手を付けるべきか迷ってしまう」
「不安から全範囲を見直そうとして、かえって時間を浪費してしまう」
「重要ポイントや暗記の優先順位が整理できず、知識が断片的なまま本番を迎えてしまう」
宅建試験は、直前期の限られた時間で得点源を確実に押さえることが合否を左右します。特に出題率の高い分野に加え、法令で定められた数値や期間、契約・手続きの流れを重点的に覚えることで、合格に大きく近づけます。
この記事では、宅建試験直前に覚えるべき重要ポイントと、暗記効率を高める具体的な方法を解説します。短期間で得点力を向上させたい方は、ぜひ参考にしてください。
宅建試験直前に覚えることとは?効率的な学習の全体像
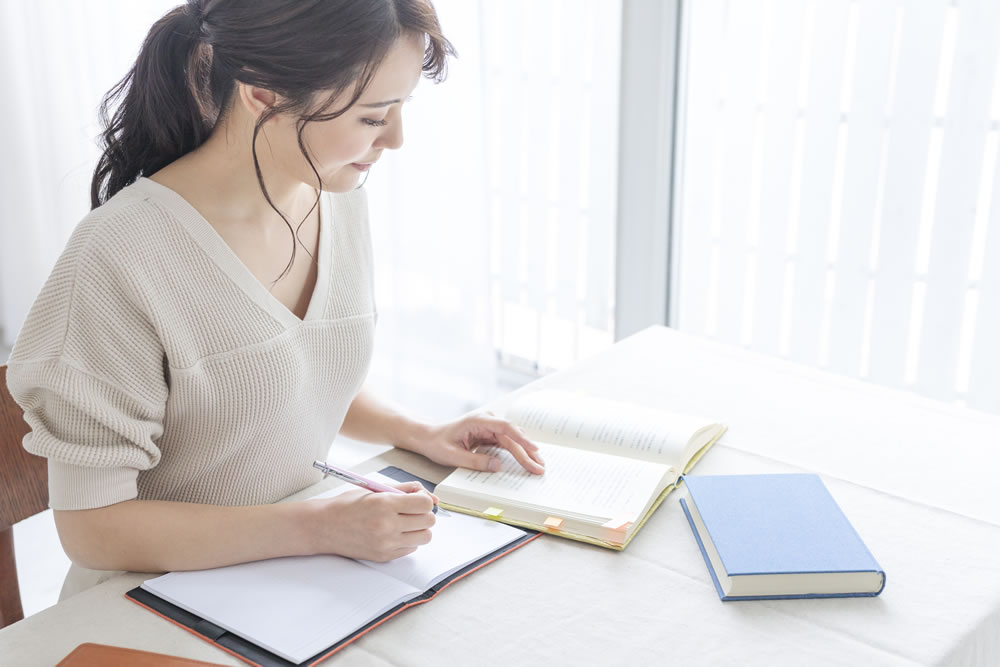
宅建試験の直前期は、全範囲を復習するよりも、得点源となる頻出分野に絞って学習しましょう。限られた時間で成果を上げるには、配点の高い宅建業法や民法を優先的に仕上げることが重要です。
また、暗記効率を高めるには、集中できる学習環境が欠かせません。静かな場所で、必要な教材やまとめノートをすぐ手に取れる状態にしておくことで、記憶の定着が早まります。効率的な直前対策は、「何を覚えるか」と「どこで学ぶか」の両方を意識することが重要です。
学習環境を整えたい方は、専用自習室と個別サポートを備えたメダリストクラブ宅建士講座の活用も効果的です。(自習室の利用には別途料金がかかります。)
宅建直前に覚えるべき重要ポイント

宅建試験の直前期は、全範囲を網羅するよりも、出題率の高い論点を確実に押さえることが重要です。ここでは科目別に、頻出分野を整理して解説します。
宅建業法の頻出論点
宅建業法は配点が高く、短期間で得点を伸ばしやすい科目です。特に以下の頻出論点は直前期に必ず確認しておきましょう。
・35条書面
重要事項説明書のことで、契約前に交付し、宅建士が記名して説明します。記載事項や説明者の資格が問われやすく、説明義務違反は契約解除や損害賠償の対象になります。
・37条書面
契約成立後に交付する契約内容の書面です。交付時期(契約締結後)、記載事項、記名の有無を正確に覚えましょう。
・8種制限
クーリングオフ制度、損害賠償額の予定等の制限、手付額の制限・解約手付、自己の所有に属さない宅地建物の売買契約締結の制限、手付金等の保全措置、割賦販売特約の解除等の制限、所有権留保等の禁止、契約不適合責任の特約制限の8項目です。各制限の対象時期や例外規定がよく出題されます。
これらは毎年のように出題されるため、条文や数字を赤シートや一問一答で繰り返し確認し、迷いなく答えられる状態に仕上げましょう。
民法等の頻出論点
民法は丸暗記で解ける問題ばかりではなく、事例をもとに判断する応用力が求められる科目です。そのため直前期は、全範囲の詰め込みよりも、出題頻度が高く得点に直結する以下のような分野を重点的に確認しましょう。
・契約解除
催告解除・無催告解除の要件や、手付解除の期限を正確に覚えます。契約形態によって解除要件が異なるため、借地借家契約や請負契約など特有の規定も押さえましょう。
・消滅時効
原則は10年、短期は5年など、期間の区別が重要です。改正民法後の期間計算や更新・完成猶予の規定も確認します。
・借地借家法
契約期間、更新の可否、正当事由制度などがよく問われます。特に更新拒絶の条件や手続きは混同しやすいポイントです。
・区分所有法
管理組合の権限、規約の制定・変更、集会の決議要件などが出題されます。数字や割合は一覧化して覚えると効率的です。
混同しやすい数字や事例は過去問で比較しながら確認し、理解と適用力を短期間で固めましょう。
法令上の制限の頻出論点
法令上の制限は数字や区分が明確で、短期間でも得点しやすい分野です。直前期は以下の項目を重点的に確認しましょう。
・都市計画法(用途地域)
13種類の用途地域と建築可能用途を整理します。角地緩和による+10%や、防火・準防火地域の規制も頻出です。
・建築基準法(建ぺい率・容積率)
建ぺい率は敷地面積に対する建築面積の割合、容積率は延べ面積との割合です。数字の入れ替えによるひっかけが多いため、一覧表の確認が必要です。
・国土利用計画法
許可が必要な土地取引の面積基準や届出期間を確認します。
・農地法
農地転用の許可区分(第3条・第4条・第5条)と権限者を覚えます。
・宅地造成等規制法
宅地造成の許可要件や工事中止命令の条件を押さえます。
・土地区画整理法
事業の施行者、仮換地の指定、清算金の仕組みを確認します。
都市計画法と建築基準法を優先的に学習し、それ以外の法律は過去問で間違えた部分だけをテキストで確認すると効率的です。
税・その他の頻出論点
税・その他の分野は配点は低めですが、数字や規定を覚えれば得点につながりやすく、直前期の仕上げに適しています。以下の項目を重点的に確認しましょう。
・不動産取得税
原則税率4%ですが、土地と住宅は軽減税率として3%となっています。軽減措置や課税標準の特例(新築住宅120㎡まで軽減など)は要確認です。
・登録免許税
所有権保存登記は0.4%、移転登記は2%(住宅用軽減で0.3%)など、税率と軽減措置を覚えます。
・印紙税
契約金額ごとの税額表を確認しましょう。特に1,000万円や5,000万円など端目の金額を間違えないよう注意が必要です。
・固定資産税
標準税率1.4%。住宅用地特例(200㎡以下は1/6など)や課税標準の特例も重要です。
・その他の法令
景品表示法の規制(景品類の上限額)や地価公示法の基準日(毎年1月1日)も頻出です。
これらは短時間で暗記できるため、まとめノートや暗記カードで一気に仕上げ、試験直前の最終確認リストとして活用しましょう。
宅建直前期に暗記を仕上げる4つの方法

試験直前は、限られた時間で知識を確実に定着させる学習法が重要です。ここでは、効率的に暗記を進めるための4つの方法を解説します。
1. 赤シートと一問一答で反復学習する
直前期は、赤シートと一問一答形式を使った短時間反復が効果的です。赤シートで重要語句を隠し、記憶を呼び起こす練習を繰り返すことで、短期間でも定着が進みます。
一問一答形式は答えをすぐ確認できるため、弱点の発見にも最適です。特に宅建業法の数字や期間、法令上の制限の数値などは、この方法で繰り返すと忘れにくくなります。
時間が限られる直前期は、長文読解よりも瞬発力のある暗記法が有効です。記憶を呼び出す訓練を重ね、本番で迷わず解答できる状態を目指しましょう。
2. 科目ごとの得点配分を意識して時間を配分する
直前期は、配点の高い科目から優先的に学習することが重要です。宅建試験は、以下のように出題数に差があります。
・宅建業法:20問
・民法等(権利関係):14問
・法令上の制限:8問
・その他の関連知識:8問
特に宅建業法は全50問中20問を占めるため、1問正解するごとの得点割合が高く、合否に直結します。全科目を均等に復習すると効率が下がり、得意分野の強化も遅れます。
過去問や出題傾向を参考に、配点の高い分野や得点源となる科目に時間を集中させることが、短期間で合格率を高める最も効率的な方法です。
3. 模試や過去問の間違いを重点的に覚える
直前期は、新しい問題集に手を出すより、これまで解いた模試や過去問の間違い直しを徹底する方が効率的です。間違えた問題は、自分の理解不足や暗記漏れが原因で、再出題の可能性が高い重要ポイントでもあります。
例えば、民法の解除要件や宅建業法の広告規制などは、出題パターンや数字の使い回しが多く、一度覚え直すだけで正答率が大幅に向上します。間違いノートや過去問の印を付けた問題を中心に復習し、根拠や条文の内容まで確認すると理解が定着します。
短時間で弱点をつぶすことが、直前期に得点力を最大限引き上げる近道です。
4. 一問一答の問題集でスキマ時間を活用する
通勤・通学や家事の合間などの細切れ時間は、直前期の暗記に最適です。一問一答の問題集を使えば、苦手分野だけを集中的に演習することも可能です。
宅建過去問や一問一答問題集、短時間での反復に向いており、試験当日まで知識を新鮮な状態に保てます。
さらに、暗記効率を最大化するには集中できる環境も必要です。静かで快適な学習空間を確保したい方は、メダリストクラブの自習室の利用がおすすめです。(自習室の利用には別途料金がかかります。)
宅建直前期にやってはいけない3つの行動
試験直前は、何をするかだけでなく、何を避けるかも重要です。ここでは、宅建直前期にやってはいけない3つの行動について解説します。
1. 新しい教材や参考書に手を出す
直前期に新しい教材や参考書に手を出すと、内容を消化しきれず混乱しやすくなります。これまで積み重ねた知識や解答パターンと異なる説明や出題形式に触れることで、これまでの学習の軸がぶれ、復習時間も削られてしまいます。結果として、得点効率が大きく低下するでしょう。
また、新しい問題集には初見の知識や細かい情報が多く、重要度の低い項目に時間を取られてしまうこともあります。宅建試験の直前期は、全範囲を網羅するよりも、出題頻度の高い論点を繰り返し確認する方が得点につながります。
新しい知識の追加よりも、これまで学んだ内容を確実に定着させることが合格への近道です。
2. 暗記範囲をむやみに広げる
試験直前に焦って暗記範囲を広げると、どの分野も中途半端な仕上がりになり、得点力が安定しません。覚えたつもりでも、知識が曖昧なまま本番を迎えるリスクが高まります。
直前期に全範囲を浅く触れるよりも、出題率が高く配点の大きい分野を深く確実に覚える方が得点につながります。具体的には、宅建業法や民法等の頻出項目、法令上の制限の数字など、毎年出題されるテーマを中心に絞り込みましょう。
出題頻度と得点配分を基準に優先順位を決め、重要項目を繰り返し確認して記憶を定着させることが直前期の学習で効果的です。
3. 生活リズムを崩す
徹夜や不規則な生活は集中力や記憶力を低下させ、試験当日のパフォーマンスに直結します。特に睡眠不足は、暗記した内容の定着や判断力にも悪影響を与えます。直前期ほど、安定した生活リズムを保つことが重要です。
具体的には、試験時間に合わせた就寝・起床を少なくとも1週間前から習慣づけ、体内時計を本番モードに整えましょう。また、栄養バランスの取れた食事や適度な運動も、集中力維持に有効です。
健康状態を万全に保ちながら学習を続けることが、知識を確実に発揮するための土台となります。
宅建試験直前期の講座はメダリストクラブがおすすめ

宅建試験直前期は、全範囲を網羅しようとするよりも、頻出論点を確実に覚え、得点効率を高めることが合格への最短ルートです。特に宅建業法や民法など、出題率の高い知識を重点的に仕上げましょう。
また、暗記の効率は学習環境にも大きく左右されます。集中して学べる環境や、直前期に特化した学習計画を活用することで、限られた時間でも最大限の効果を得られます。
本番まで知識を磨き上げたい方は、効率的なカリキュラムと個別サポートが揃う「メダリストクラブの宅建士講座」や、集中力を高められる「メダリストクラブの自習室」を活用し、合格を確実に引き寄せましょう。(自習室の利用には別途料金がかかります。)