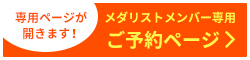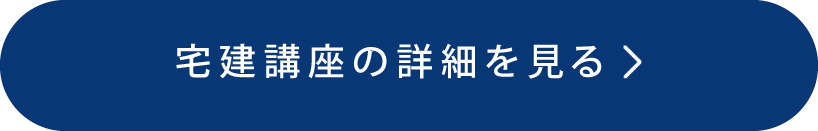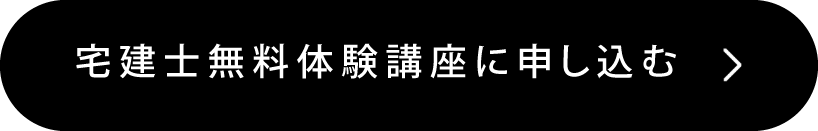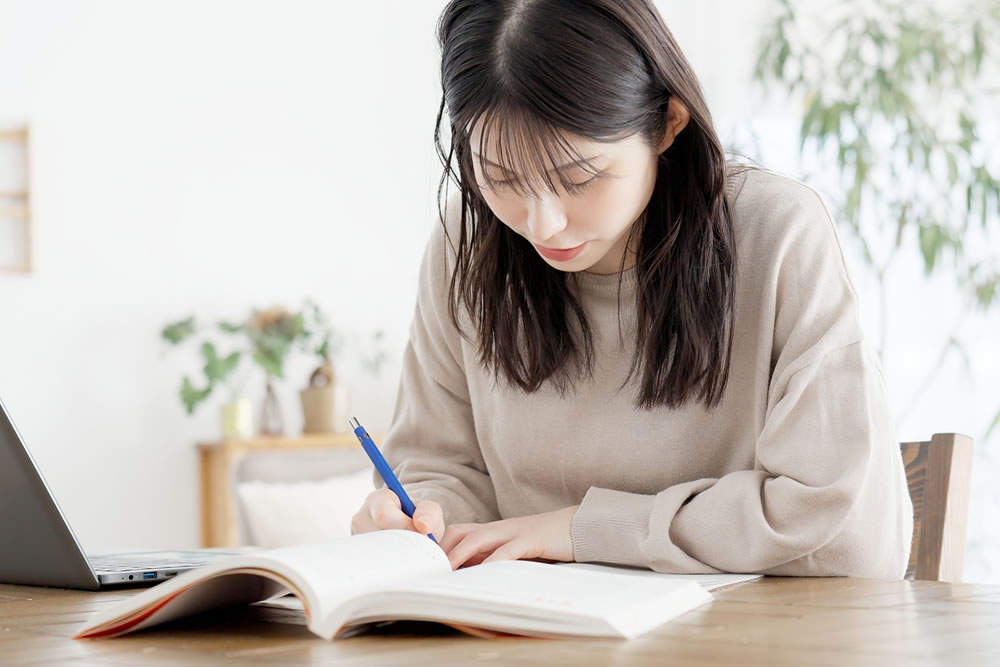宅建試験問題のおすすめな解き方4選!科目ごとの順番や時間配分を解説
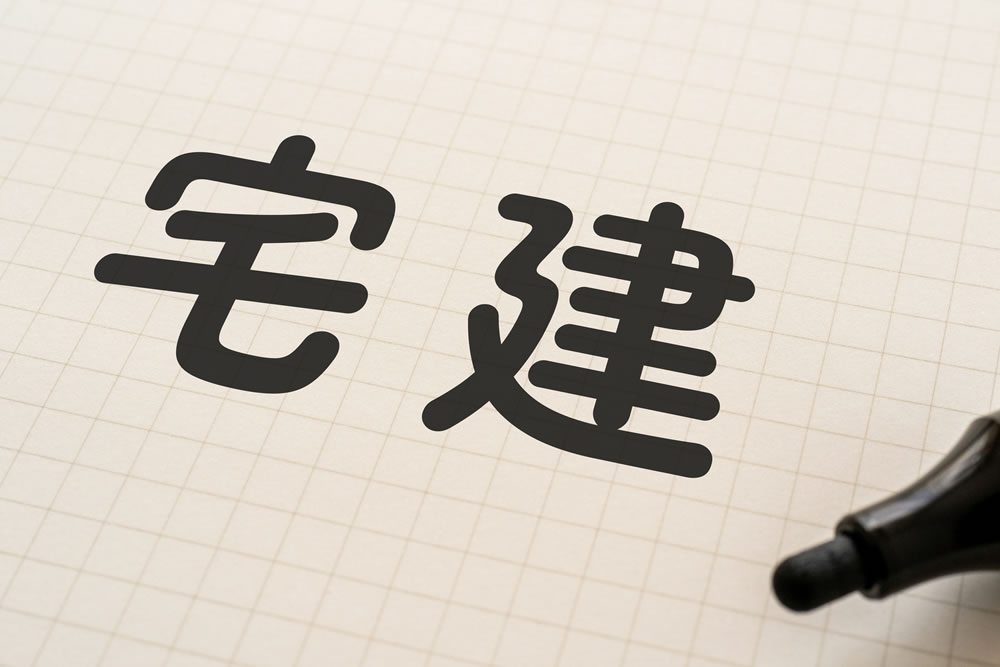
- カテゴリー
- タグ
-
- #宅建業法
このページは約6分で読めます。有意義なページになっていますので、最後までご覧ください。
宅建試験問題のおすすめな解き方4選!科目ごとの順番や時間配分を解説
「勉強してきたけど本番で力を出せるか不安」
「試験の時間が足りなかったらどうしよう」
「分からない問題でつまづいたら焦りそう」
実際に受ける試験は独特の雰囲気があり、緊張したり力が発揮できるか不安になったりする方も多いのではないでしょうか。試験本番では、今までの努力を100%発揮したいものです。
そこでこの記事では、宅建試験本番で本来の力を発揮できるように「おすすめの試験の解き方」「科目ごとでおすすめな解き方の順番」「科目ごとの時間配分」などを、詳しく解説します。本番の試験に落ち着いて臨みたい人は必見です。
宅建試験の問題数と出題形式
まずは、宅建試験の問題数と出題形式をあらためて確認しておきましょう。
| 問題数 | 50問(45問※5問免除の場合) |
| 出題形式 | 4肢択一のマークシート形式 |
宅建試験は4肢択一の出題形式になっているため、暗記しておけば解けるような問題があります。しかし中には、長文の判例を最後まで読まないと答えが導き出せないような難問もあるため、注意が必要です。
また「個数問題(『この4肢の中で正しいものはいくつあるか?』という問題)」に関しては、すべての選択肢の正誤を判断する必要があるため、問題にかかる時間が長くなります。
1つの問題を考えすぎると時間が足りなくなるため、配分を考えながら解くのがコツです。あらかじめ過去問や模擬試験などで、本番に合わせた「時間の使い方」を練習しておくようにしましょう。
宅建試験問題のおすすめの解き方4選
宅建試験に合格するためには、本番での「問題の解き方」が重要です。ここでは、宅建試験に合格するためのおすすめの解き方を4つ解説します。
1問にかける時間をあまり意識しない
宅建試験は、120分の試験時間で50の問題を解く必要があります。そのため、1問あたりにかける時間は2分以内の計算です。
しかし、権利関係や宅建業法などの科目によって問題数やボリュームが違います。例えば、1分で解ける簡単な問題や、5分かかって解く難問などが出ることも考えておかなければいけません。
1問の時間を気にしすぎるあまり試験に集中できない恐れがあるため、問題をブロック分けした時間配分で解いていくようにしましょう。
科目に応じた時間配分で解いていく
宅建試験は、科目ごとに時間を決めた解き方がおすすめです。「1問あたり〇分」という解き方よりも、科目ごとのブロックに分けたほうが解きやすくなります。
例えば「民法には時間をかけたいから30分かけてじっくり解く」「行政法は慎重に解きつつも得意だから20分でさくっと解ききる」などに分ける解き方です。
科目ごとに時間を決めておくと自分のペース配分で解けるため、気持ちの面でも落ち着いて試験に挑めます。
得意な科目から解いていく
宅建試験は1問目から解く決まりはありません。そのため、得意な科目から先に解いていくようにしましょう。
解きやすい問題から進めていけば、時間がかかる「判例問題」や「計算問題」に余裕をもって挑めます。試験によっては1問目に判例問題が出たこともあり、ペースを崩された人が多く見受けられたケースもあります。
問題をスムーズに解いていくことが、合格に大きく影響するといっても良いでしょう。また、試験が始まったらまず問題全体を確認してどんな問題があるのかを確認するのもおすすめです。全体を確認して、解きやすい問題から手を付けるようにしましょう。
10問ごとにマークシートを塗る
宅建試験は、4肢択一のマークシート方式の試験です。1問ごとにマークしていく必要がありますが、注意が必要です。
1問づつマークする場合、問題と解答がずれたときに再度消して塗りなおす作業が必要です。マークには、力を入れて濃いめに記載することが多いため、消す作業に時間がかかります。また、1問解くごとに問題用紙とマークシートを交互に目を移す必要があるため、疲れやすいのも特徴です。
一度解いた回答の番号を問題に記載しておいて、あとでまとめてマークすればミスや疲れを防止できます。50問をまとめてマークするのが不安な方は、10問ずつに分けてマークすると良いでしょう。
【科目別】宅建試験の時間配分を考えた解き方

ここでは、宅建試験に出題される問題の「時間配分」を考えた解き方を、科目別に解説します。問題の数によって、解く時間を調整することが必要です。
| 解く順番の例 | 問題にかける時間 | 1問にかける時間 | 問題数 |
| ①宅建業法 | 短め | 約1~1.5分 | 20問 |
| ②権利関係 | 長め | 約3~5分 | 14問 |
| ③法令上の制限 | 短め | 約1~1.5分 | 8問 |
| ④税・その他 | 短め | 約1~1.5分 | 8問 |
上記の表を参考に、それぞれ見ていきましょう。
宅建業法
宅建業法は、一番問題数が多い科目ですが、問題にかける時間は短めに設定するのをおすすめします。20問というボリュームになるため、じっくり時間をかけにくいからです。
また、宅建業法の問題は過去の試験問題をもとに構成されているケースが多いため、過去問などをしっかり勉強して問題に慣れていれば、解きやすいのがほとんどです。
権利関係
権利関係は、宅建業法の次に問題数が多い科目です。さらに1問ごとの問題文が長く、さくさくと解いていくのが難しいため苦手としている方は多いと言えます。
例えば判例文から出題される場合、問題をすべて読まないと答えが分からないような難問があり、1問に対して5分近い時間がかかるケースがあります。
宅建業法などの他の科目をできるだけ早めに解き終わって、じっくり時間をかけられるような「時間配分」を考えましょう。
法令上の制限
法令上の制限は、不動産に関する専門用語が多く出題されます。不動産用語を暗記しておけば、解く時間はあまりかかりません。
10年分の過去問などを繰り返し勉強しておけば解ける問題も多いため、時間をかけずに解くようにしましょう。
税・その他
この科目も暗記がメインでの勉強になるため、過去問やテキストで専門用語を覚えておけば解きやすいです。そのため、1問にかける時間は短めに設定しましょう。なお、統計問題は試験直前に最新情報を確認しておけば解けるため、1問目に解くのもおすすめです。
宅建試験で点が取りやすい解き方の順番

宅建試験本番では、点数を取りやすい問題や、時間をかけて考える問題を優先的に解く必要があります。ここでは、宅建試験で点数が取りやすい解き方の順番を解説します。
| 解く順番の例 | 問題の番号 |
| ①宅建業法 | 問26~45 |
| ②権利関係 | 問1~14 |
| ③法令上の制限 | 問15~22 |
| ④税・その他 | 問23~25 |
| ⑤5問免除問題 | 問46~50 |
【①宅建業法】13:00~13:30
試験が開始されたら、宅建業法から解き始めるのがおすすめです。暗記している内容が多いため、途中から解いていくよりも答えやすくなります。
20問を30分で終わらせる必要があるため、分からない問題は飛ばしてあとで解くようにしましょう。
【②権利関係】13:30~14:10
宅建業法の次に、権利関係を解くようにしましょう。問題文が長くじっくり考える問題も多いためある程度時間をかける科目です。
一番問題数が多い宅建業法を解くことによって安心できれば、落ち着いて臨めます。時間は40分を想定しているため、参考にしましょう。
【③法令上の制限】14:10~14:30
宅建試験の2大重要科目でもある宅建業法と権利関係を解き終えたら、あとはさくっと解ける科目になります。ここからは残り時間も少ないですが、問題に対して正誤を答えるシンプルなものが多いため、20分以内で終わらせましょう。
【④税・その他】【⑤5問免除問題】14:30~14:45
税・その他、5問免除問題には問題数が多いものもありますが、落ち着いて解くようにしましょう。この時点で残り時間が少ないですが、焦りは禁物です。
過去問や暗記していれば解ける問題も多いため、しっかり点数を稼ぎましょう。
【見直し】14:45~15:00
最後に、飛ばしていた問題の解答や見直しを行います。とくに計算問題は、再計算してみるのをおすすめします。計算間違いや勘違いなどで、答えが間違っているケースが意外と多いからです。
なお、マークシートのズレがないかの確認や、名前の記入漏れなども確認するようにしましょう。
宅建試験の解き方で絶対に避けたい2つの注意点

試験当日は、今まで努力してきた自分を信じて臨むようにしましょう。そのためには、小さなミスがないように落ち着いて試験を受けることが大切です。
ここでは、試験当日の問題の解き方で避けるべき2つの注意点を解説します。
マークミス
宅建試験で一番怖いと言えるのが、マークミスです。問題の解答を、違う場所にマークすることで起こります。
例えば、以下のような状況です。
問23の解答を、1つ隣の解答欄「問24」にマークしたケース
問題を途中から解き始めていたが、問1からの解答順でマークしたケース
1の場合、問23以降の問題がすべてズレてマークしている恐れがあります。また、2の場合は試験の途中で気づきやすいですが、訂正に時間がかかってしまうケースです。
自己採点で合格点をクリアできていても、マークミスが原因で不合格(実際に合格・不合格にかかわらず点数は開示されません)になるのは悔しいものです。このような失敗を防ぐためには、本番でマークシートのズレがないか何度も確認するようにしましょう。
時間配分の間違い
本番の宅建試験では、過去問にも出題されていないような新しい切り口の問題などが出題されるケースがあります。そのため、想定していた時間内に問題が解けず、パニックになる方もいるかもしれません。
しかし基本的には、今まで勉強してきた基礎的な内容構成で作られています。どうしても分からない問題は飛ばして、分かる問題から解いていった方が点数を稼げます。
深呼吸を行い、一度気持ちを落ちつかせて臨むようにしましょう。
まとめ

宅建試験は、問題を解く順番や時間配分を把握しておくことで、合格に近づけると言っても良いでしょう。合格点を左右する「宅建業法」や「権利関係」を中心に、自分が解きやすい順番で合格を目指しましょう。
また、科目ごとにかける時間も異なります。得意な科目はそれぞれ違うため、この記事の内容を参考に、自分が解きやすい方法で本番に臨むようにしてください。
メダリストクラブの宅建講座なら、専門の講師が効率的な学習方法を指導し、最新の試験傾向に基づいた対策を提供してくれます。また、模試や過去問演習などのサポートも充実しており、本試験の時間配分を考えながら効果的に学習を進めることが可能です。まずは一度、無料体験講座に参加してみましょう。