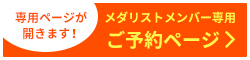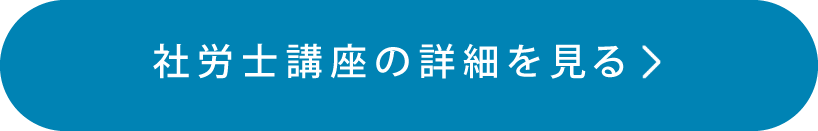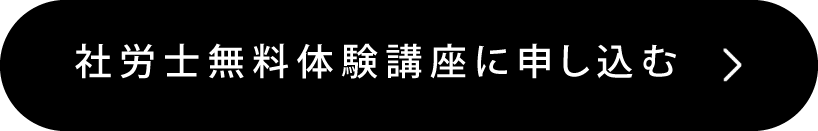社労士の仕事内容は?

- カテゴリー
- タグ
このページは約6分で読めます。有意義なページになっていますので、最後までご覧ください。
社労士の仕事の全貌をチェック!具体的な業務内容から働き方、年収まで幅広くご紹介。これから資格を取得して社労士を目指そうとされている方必見です。

昨今注目を集めている社会保険労務士(以下、社労士)が、具体的にどんな仕事をしているかご存じですか?社労士は、企業の労働や社会保険に関わる重要な手続きをサポートし、企業の成長や従業員の働きやすい環境を作るためのアドバイスをする専門家です。本記事では、社労士の仕事内容を具体的に解説し、さらに年収や資格取得のための情報もお届けします。これからキャリアチェンジを考えている方や、社労士の仕事に興味がある方はぜひ最後までご覧ください!
社労士とは

労働・社会保険の問題の専門家として、(1)書類等の作成代行、(2)書類等の提出代行、(3)個別労働関係紛争の解決手続(調停、あっせん等)の代理、(4)労務管理や労働保険・社会保険に関する相談等を行うのが、社労士です。より簡潔に、社労士は企業における「ヒト」の問題に関する専門家と言い換えることができます。
社労士の仕事内容
社労士の仕事内容は、社労士法に規定されています。注意したいのは、社労士にしかできない業務が存在するという点です。これを独占業務と呼び、1号業務と2号業務がそれにあたります。
このほか、特定社労士のみ行うことができる「紛争解決手続代理業務」があります。
| 1号業務 ※独占業務 |
| ・労働保険、社会保険の書類作成、提出代行 (例)従業員の入退職手続きなど ・健康保険、雇用保険の給付手続き、雇用関係助成金申請 (例)産休育休や傷病手当金の申請など |
| 2号業務 ※独占業務 |
| ・労働社会保険諸法令に従う帳簿書類の作成 ・賃金台帳の作成請負 ・就業規則や各種労使協定の作成 |
| 3号業務 |
| ・労務管理や社会保険などに関する相談、アドバイス、コンサルティング (例)人事評価などの社内制度構築など ・公的年金の相談、経営労務診断 |
| 紛争解決手続代理業務 ※特定社労士のみ |
| 労働にかかわる経営者と労働者間のトラブルを、裁判外の「あっせん」「調停」「仲裁」という手続きにより解決する |
参考:社会保険労務士法第27条 , 全国社会保険労務士会連合会
社労士としての働き方

社労士として仕事をするためには、社労士試験に合格後、全国社会保険労務士会連合会の社労士名簿に登録する必要があります。登録種別は「開業」「法人の社員」「勤務」「その他」の4種類があり、それぞれの種別によって業務の範囲などが異なります。
開業・法人の社員
「開業」は、自己の名で業として社労士の業務を行うための登録種別です。個人事務所として社労士事務所を構える場合はこの登録を行うことになります。また、「法人の社員」は社労士法人を設立する場合の登録種別です。法人に雇用されて勤務する従業員ではなく、出資者という立場になるため開業社労士に近い立場になります。業務範囲も開業の場合と同じです。
開業・法人の社員の社労士は主に、企業と労務に関する顧問契約を結んだり、社会保険や助成金の申請手続きをスポットでサポートします。
個人事業主・会社経営者の立場になるため、仕事の獲得や報酬設定、トラブル対応などはすべて自分で行う必要があります。しかし収入に上限はなく、努力すれば高収入も期待できる働き方であるといえるでしょう。
| 開業・法人の社員の1日のスケジュール(例) | |
| 9:00〜 | 顧問先からのメール確認官公庁からの電話対応 |
| 11:00〜 | 新規取引A社との商談 |
| 13:00〜 | 顧問先の給与計算 |
| 14:00〜 | 労働局の助成金センターへ助成金の申請 |
| 15:00〜 | 新規顧問先開拓の営業 |
| 16:00〜 | 顧問先Bの労務相談(オンライン)顧問先Cの就業規則変更届作成 |
| 18:00 | 業務終了 |
勤務
「勤務」は企業に勤務し、人事労務部門などに所属しその企業内でのみ社労士業務を行う登録種別です。
この登録種別の場合、自分が所属していない会社の社労士業務を業として行うことはできない点が、開業・法人の社員である社労士とは大きく異なる点です。
勤務社労士は会社員なので、安定した収入を確保しながら人事労務の実務経験を積むことができます。
| 事業会社の企業内勤務社労士の1日のスケジュール(例) | |
| 9:00〜 | 出社・朝礼 |
| 10:00〜 | 自社従業員の各種手続・入退社に関わる手続申請・育休申請 |
| 12:00〜 | 昼休憩 |
| 13:00〜 | 給与計算 |
| 15:00〜 | 新入社員に対しオリエンテーション研修・勤怠管理システムの使い方・フレックスタイム制の説明・確定拠出年金の加入手続 |
| 16:00〜 | 官公庁からの問い合わせ対応 |
| 17:00〜 | 自社の経営会議で就業規則の変更について打ち合わせ |
| 18:00 | 業務終了 |
その他
「その他」登録の社労士は、社会保険労務士法に規定された社労士の業務を社労士として行うことはできず、そのため、無資格者でもできる労働相談等を行う際に「社労士」と名乗って相談業務を行うこともできません。
社労士として業務を行うことはできなくても、社労士会の会員として、他の登録区分の会員と同様に連合会や所属する都道府県社労士会等が行う研修等への参加ができ、連合会や都道府県社労士会等から各種情報を得られる、他の社労士との人的ネットワークを形成することができる等のメリットがあります。
社労士として実際に仕事を始める前に、情報収集や人脈作りのために登録料が比較的安価な「その他」登録から始めるという方法もあります。
参考:茨城県社会保険労務士会|社労士と社労士制度 よくある質問(Q&A FAQ)
社労士の年収
厚生労働省の職業情報提供サイトによると、社労士の平均年収は947.6万円とされています。年齢別にみるとばらつきはあり、もっとも高い年収層は45〜49歳で1580.02万円となっています。
また70歳以上の年齢層でも429.48万円となっており、高年齢でも現役並みの収入が期待できます。高齢化や年金問題があるなかで、高齢になっても現役並の所得を得られる可能性がある社労士は、今後ますます人気資格になっていくと予想されます。
社労士の仕事の将来性
社労士は、昨今話題になっている働き方改革への対応や人材不足などの企業経営者が抱える問題を解決しうる存在です。雇用関係助成金の申請支援や人事評価制度コンサルティングを行うことで、企業へ制度的に還元し、働く人のモチベーションに直接的にアプローチする提案ができるのは、社労士ならではの役割といえるでしょう。
また、人事関連の業務を中心とした企業のDX化(デジタル化の促進、情報セキュリティ強化など)や電子手続きについての相談にもニーズがあります。社労士が官公庁に対して行う各種申請や手続きも時代の流れとともに電子化が進められており、総務省が運営する「e-Gov」がその一例です。このような情報をいち早くキャッチし、煩雑で手間がかかると思われやすいDX導入を支援したり、手続きの代行などを請け負ってくれる社労士は、中核業務に集中したい企業の経営者にとってなくてはならない存在です。
定型的な手続業務などはAIなどによって効率化され、申請にかかる人的リソースは大幅に削減されつつあります。一方で頻繁に行われる法改正への対応をしながら、上記のようなそれぞれの企業に合ったコンサルティングを行うことは現状のAIなどには難しいことでしょう。
社労士に向いている人
社労士は、細かい作業に集中して取り組める人に向いているといえるでしょう。開業の場合も勤務の場合も給与計算や社会保険関係手続きなど、ミスが許されないものです。企業の人事や経理などの事務職の経験がある人は馴染みやすいかもしれません。
しかし社労士は手続きなど事務作業ばかりの仕事ではありません。3号業務領域でも活躍するためには、コンサルティングに必要な傾聴力や説明力、コミュニケーション力も必要です。営業や販売などの対面スキルを持つ人も、社労士業務のなかで強みを発揮できるでしょう。
社労士になるためには
ここまで社労士の仕事内容についてご紹介してきましたが、この章では実際に社労士になるためにどのようなプロセスを踏む必要があるかを解説します。
| 1.社労士試験に合格する 2.全国社会保険労務士会連合会の社労士名簿に登録する |
社労士試験に合格する
社労士試験は、1年に1回、毎年8月に実施される試験です。
| 社労士試験の概要 |
| ・試験は1年1回、毎年8月に実施される ・受験資格として「学歴」「実務経験」「社労士以外の資格」のいずれかを満たす必要がある ・主要な試験科目は10科目。労働関係の法令や、社会保険関係法令などから出題される ・合格率は例年6〜7%で難関試験といわれている |
全国社会保険労務士会連合会に登録する
社労士として活動するには社労士試験合格後、実務経験2年以上または事務指定講習の修了を経て、全国社会保険労務士会連合会(通称:連合会)が備える社会保険労務士名簿に登録が必要です。
登録の申請は、開業する事務所や勤務先事務所の所在地、または居住地の住所がある都道府県の社会保険労務士会に入会して行います。
詳細は全国社会保険労務士会連合会のホームページで紹介されていますので、気になる方はご覧ください。
参考:全国社会保険労務士会連合会|社労士を目指す|社労士の登録申請について
まとめ
最後に、今回の記事の要点をまとめます。
◉社労士は労働・社会保険の問題の専門家
◉社労士の平均年収は947.6万円
◉合格後は独立開業も、会社員としてキャリアアップすることも可能
◉社労士になるためには社労士試験という国家試験に合格する必要がある
社労士の仕事内容は、一般の方にはなじみがあまりなくイメージしづらいかもしれません。しかし労働問題や社会保険手続きなど、企業の重要な課題を解決する専門家であり社会のなかでも重要な役割を担っています。

メダリストクラブの社労士講座は、独自にカスタマイズしたオリジナル教材で合格に向けた効率のよい試験対策が可能です。
これから社労士を目指してみようという人は、ぜひメダリストクラブの社労士講座を検討してみてください。